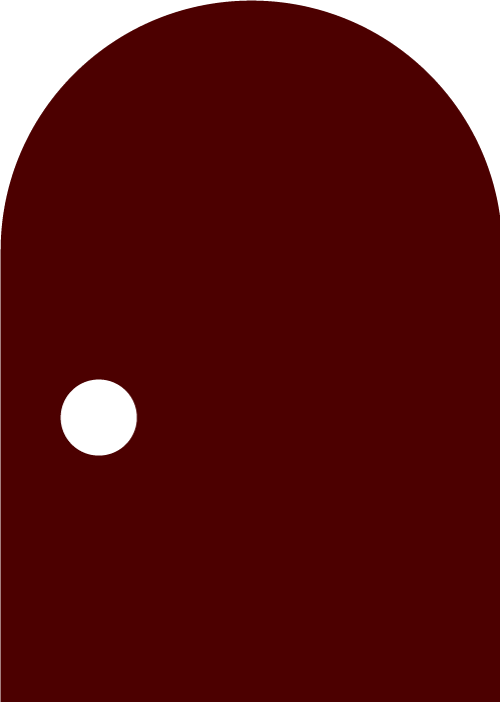YouTube始めました
先日新しいYouTubeチャンネルの1本目の動画を公開しました。
このチャンネルを始める経緯を話しているのですが、これはアーティストや音楽家がAIと共に生きていくにはYouTubeをやっていないと「話にならない」と感じたからというのも理由の1つです。
音楽をやる上で語らざるを得なかったり、アーティストとの対談もどんどん撮っていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。
音楽AIを味方にすべきか、敵にすべきか
さて本題です。
本日のテーマは「音楽AIが変える、アーティストの未来:本当に恐れるべきか、味方にすべきか」
自分の楽曲の「楽しい」という感覚のみで突き進んでいるのですが、やはり中には仕事の目的を果たすために「スピード」や「量」が必要な作曲もあります。
この「スピード」や「量」というのは職業作曲家であれば鍛えていくべき部分なのですが、根性だけではなく今の時代を上手く活用すべきだとは考えてるんです。
そこで出てくるのが「AI」です。
私たち音楽クリエイターにとって、音楽AIは今や避けられない存在になってます。テクノロジーの急速な進化は、創作活動に大きな影響を与えようとしています。
今日は、音楽AIと向き合う一人のアーティストとして、率直に、「音楽家やアーティストがAIとどう関わるか」という部分で私の考えを共有したいと思います。
音楽AIの現状
音楽AIは今、驚くべき速度で進化しています。メロディー生成、作曲支援、さらには特定のアーティストのスタイルを模倣するなど可能になってきました。
先日、Suno AIやSOUNDRAWを触ってみましたが、驚きましたね。
この技術は脅威であるか?と問われると全くそうは思いませんでした。
何となくですが、イラスト系のAIと比べるとその界隈ほど盛り上がってない気もしています。
AIの音楽創作に対して、音楽業界は二分されています。
メリット派は、AIを創作の「拡張ツール」として捉えて、作曲の初期段階でのアイデア出し、作曲の効率化、新しい音楽表現の可能性を評価していますよね。
一方、デメリット派は、人間の創造性の軽視、著作権の問題、アーティストの独自性が失われることを懸念しています。
このデメリット側でよく言われている部分は、音楽家目線で言うと「そうか?」で済ませるほどのレベルと感じました。
やはりDTMの世界でも人間らしさを求めた打ち込みをするが、やはり人間が演奏したものには敵わないというのが現状です。(打ち込みの方がよいジャンルは別です)
そもそもやはり「誰が演奏しているか?」という部分も音楽の感動の一部だと考えているのでバックグラウンドのないAIが作った音楽にはその部分が足りない。
なんならメリット側の評価されている点も、まだまだ精度が甘く本当に一部分になってしまっています。
また音楽AIは利用における著作権課題もクリア出来ていません。
結論的には
音楽AIは脅威でも救世主でもない。
音楽作ってる音楽家側から見ればまだまだだし、人が演奏してるものには敵わない。
DTMで行うヒューマナイズ(人間らしくする)みたいな話じゃなくて、作り手のバックグラウンドとか想いとか、結局そういう物に心動くんだよな。
利用方法としてどんなものがあるか考えると
生成された音は使わないとして
・レファレンスにする
・メインジャンル以外の勉強
・量産のためのアイデア
脳のリソースを一部を預けるみたいな使い方がいいかなと思います。ただこれのために課金するかというと、しなそうだなと。
AIで収益化できるっていうけど、曲作るのが面白いみたいなとこあるから、丸々生成AIだと作るのも詰まらない。だったら違うバイトして稼いだ方が楽しい。
今後もどんどん成長するはずのAI。
他の分野では驚くほど使えるので、AIと共存しながら、自分らしい音楽を追求し続けること。それが、これからの音楽家に求められる姿勢だと思います。
以上です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも応援ありがとうございます!
私「江森亮」は個人としてのアーティスト活動と所属バンドの夜食前にクラウダーで音楽制作をしています。
公式LINEへの登録やサブスクリプションでの音楽配信、YouTubeでのMVや制作裏側公開など”聴いて””見て”くださると今後の励みになります。
\公式LINEができました/
江森亮に関する全ての情報を逃したくない人へ
▼江森亮 公式LINEの登録はコチラ↓
▼江森亮の音楽を聴いて見て応援したいという方はコチラ
・江森亮の楽曲:
https://www.tunecore.co.jp/artists?id=705928
・江森亮LAB(制作の裏側など動画)
https://www.youtube.com/@emoriryo_LAB